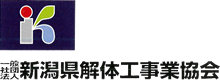解体通信
新解体 第035号(2020.02)
総務情報委員会
昨年11月の通信掲載でフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)の改正が本年4月に施行されるとお伝え致しました。解体工事に関係するフロン類は、業務用のエアコン、冷凍冷蔵機器だけではありません。今回は、「使用済みとなった断熱材」についてお話ししたいと思います。
~発砲プラスチック系断熱材の処理~
・建築用断熱材のうち、発砲プラスチック系断熱材には長年に渡り、CFC、HCFC等のフロンガスが使用されてきて、これらはオゾン層を破壊するガスであるとともに、地球温暖化への影響が大きい
・解体建物の屋根スラブの上・下部、外壁の内・外部、土間の下部に多く使用されている
・がれき類(コンクリート塊)の再資源化を推進する上では、その剥離が避けては通ることができない
・処理は、「焼却」が効果的であるが、再資源化施設があれば、それも考慮する
(ポイント)
■事前調査、準備
①断熱材の使用部位、種類、量の確認
②焼却処理施設の確認、選択
③処理委託契約の締結
■剥離、撤去
①ケレン棒、電気ピッグ等を使用する
②大きな塊で剥離する(フロンガスの放散率の軽減⇒30㎜以上なら、放散は5%以下に抑えられる)
③平バケット装着のバックホーを使用すれば、作業効率が向上する
■分別、袋詰
①吹付製品は、石膏ボード、モルタル等を取り除き、袋詰する
②成型ボード製品は、なるべく割らず、そのままの形状で取り外す
■運搬
①ダンプトラックで運搬する(深ボデー車使用で大量に)
②パッカー車で減容化して運搬する(減容時の放散は微量である)
■処理
①焼却処理基準
・燃焼ガスの温度が800度以上の状態で焼却できる
・燃焼ガスが800度以上の温度を保ちつつ、2秒以上滞留できる
・焼却により、断熱材中のフロンガスの96%を破壊できる(850度であれば、99%以上破壊可能)
②費用
・埋立処分する場合とほぼ同額である
・埋立処分すると結果的にフロンガスの全てが放散される
(具体的な効果)
出展:財団法人建材試験センター「化学物質安全確保・国際規制対策推進等報告書」
より試算
■建物解体一案件の場合
2,000m2の集合住宅の解体に伴い生じる使用済み断熱材を上記方法で処理した場合、フロンガスの残存率が最も高い場合(硬質ウレタンフォーム)
⇒約46㎏のフロンガス(約210トンの二酸化炭素に相当)が大気中に放散されることなく処理できる
210トンの二酸化炭素とは
⇒家庭から排出される二酸化炭素のおよそ37年分
⇒杉の木15,000本が1年間で吸収する二酸化炭素に相当
■日本全国で解体する建物の場合
日本全国で1年間、解体に伴い生じる使用済み断熱材を上記方法で処理した場合、
⇒約450トンのフロンガス(約200万トンの二酸化炭素に相当)が大気中に放散されない
200万トンの二酸化炭素とは
⇒50万KWのLNG火力発電所1基分(120万世帯の電力)に相当
⇒日本中の乗用車(5,700万台)が、183km(東京~静岡間)走行した際に排出される二酸化炭素に相当(乗用車には運転手一人の乗車であると仮定)
(今後の課題)
■ノンフロン断熱材の普及、推進
【関係省庁】
・グリーン購入法
・JIS法で規格製品のノンフロン製品(A種)の追加
・「公共建築工事標準仕様書」等で使用できる断熱材のノンフロン製品の限定
【建設業界】
・環境保全自主行動計画にてノンフロン製品の調達、使用の促進及び代替フロンの排出抑制
【建材メーカー】
・ボード、サイディング、パネル製品のほとんどがノンフロン化されている
・現場で直接吹付施工されるウレタンフォームは、ノンフロン化が進んでいるが、多くはフロンガスを発泡剤として使用されている・・
【解体工事業界】
・法令の周知
・法改正への適応
・現場作業員への説明並びに安全装備品着用の推進
・適正処理の推進
・再資源化処理の研究、開発
以上